総社市には児童館がありません。就園前までのつどいの広場、就学前までの子育て支援センターの利用年齢を過ぎてから、屋外は公園があっても、屋内の遊び場はありません。
これからの総社市には子どもたちが笑顔いっぱいで遊ぶことができ、親同士も交流ができる新たな環境を作り出したいと考えています。
また中学/高校生の居場所もありません。交流や自習、音楽などのさまざまな活動もできる、家でも学校でもない第3の居場所「ユースセンター」のような環境が必要ではないでしょうか。
総社市でも不登校の子どもたちは増加傾向にあります。子どもたち一人ひとりに配慮された特別の教育課程を編成し、学ぶことができる学校が「学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)」です。
「人の多いクラスで授業を受けられない」「発達障害傾向もあり馴染むことができない」「授業についていくことができない」「でも本当は学校で学びたい」という子ども一人ひとりに寄り添った環境が、これからの総社市には必要です。
市内中心部の小中学校は大規模校化している一方、郊外はますます小規模校化しています。と同時に校舎は年々老朽化していますが、建て替えの予定も現在計画にありません。
子どもたちのことを思えば、適切な学校規模とするために、校区の見直し、義務教育学校化の検討や校舎の建て替え、児童生徒が集中しすぎている大規模校を分離新設する必要性も感じています。
子どもが産まれてくる楽しみと同時に産後の不安もあると思います。その不安をなくすための伴走支援、相談、産後ケアの拡充と育児にしっかりと向き合えるようなサポートを行ってまいります。
また人口増を目指すということは、子どもが増えることでもありますので、待機とならないよう認可保育所のさらなる充実を目指し、さらなる保育士の確保に向け、一定期間市内の保育所で就労していただくことで返済不要との条件とする「修学資金貸付制度」の創設を働きかけていきます。
例として第3子以降の出産祝い金(例えばの話として、祝い金が50万円の場合は「出産時に10万円・3歳になったときに15万円・小学校入学時に15万円」と段階的な支給をし、祝い金目的ではなく、市への定住を促進していただくことを目的とします)やチャイルドシートや子ども乗せ自転車の購入補助、
また第3子以上がいる家庭には1子・2子を含めた子ども全員の18歳までの医療費無償化(現在:R5年4月より中学卒業まで無償)やその他の助成ができるよう働きかけます。
▼その他にもご意見・ご要望がある方はこちらからお声がけをお願いいたします
![[政策方針]総社の未来を担う若者のため](image/policy_3.png)
議員と同時に、創業をしている人間として、新たな事業やアイデアを形にする楽しさと共に難しさも知っています。そんな新たなことに挑戦する方々の力になりたいと考えています。特に若い方の活力はすべての世代の活力となっていき、街が自然と活気に満ち溢れてきます。
「これからを創る」その力をぜひお貸しください。共にここ総社に新たな風を吹かせていきましょう。
[やりたいこと/興味があること] ※ 各項目をクリックすると詳細をご覧になれます
総社市は岡山市/倉敷市のベッドタウンであると同時に、交通の便を生かした企業誘致も進めていくべきです。
であれば必要となるのは土地の確保です。住宅用地は空き家自体の利活用だけでなく解体の促進を行い、市外化区域を増やしていくための都市計画の見直しや地区計画を行い、
不要な公用地の売却や土地公社を活用した土地の確保を進めていく必要があると考えます。
中心部では人口が増加している一方、郊外では人口減少が加速しています。しかし総社市郊外の山、川などの自然多い環境には十分な魅力があります。それは私自身の出身は人口6,000人弱の海町であったことにも由来していると思います。
俗にいう「よそ者」であればあるほどその魅力を強く感じる。現に総社市は市外、県外からの移住者が多くなっており、その「よそ者力」を生かしたアピールや地域の魅力のさらなる発見、新たな産業を生み出すために地域活性化起業人や地域プロジェクトマネージャーなどを含めた「地域おこし協力隊」の制度こそ活用していく必要があると考えています。
これからの総社に必要なのは「協働的なまちづくり」であり、例えば駅前や商店街、子どもの遊び場や若者集う場所、観光地、郊外の魅力化をどうしていくのか、など議論をすることは沢山あります。
そのまちづくりに欠かせないのは「市民の皆様の声」です。各ジャンルごとにプロジェクトチームを組み、これからの総社市を担っていただく若い方をはじめ、様々な世代、多様な方に参加していただき意見を出し合うことが大切です。
「理想の総社を市民みんなでつくり上げていきませんか」
総社市は観光が弱いというご意見もいただきます。ですが、備中国分寺や宝福寺、豪渓に桃太郎伝説の鬼ノ城、古墳などの魅力あふれる「場所」があります。加えて太鼓や神楽などの「文化」に農業や自然の「体験」ができます。
総社市が全国屈指の福祉文化先駆都市を目指しているのであれば、高齢者や障がいのある方でも楽しめるユニバーサルツーリズムなどにも取り組んでいくことが必要です。そうして訪れてくださった方々が、さらに総社市に新たな人を呼び込んでいたく関係人口となるような戦略を立て、それを実行する組織づくりが必要と考えています。
私が所属していたそうじゃ若者塾のような、人材の育成にもっと取り組んでいく必要があると思っています。様々な分野で活躍する人を輩出することで人の輪が広がった先に多くの人材が集まり、交流し、知恵を出し合うことにより今までになかった企画や、新たな事業が産まれさらなる雇用が生まれることも期待できるのではないかと感じます。
より良い総社市にしていくためにも、中高生を中心としたこども議会の開催や主権者教育なども含め、これから市のために何かしたいと思い、考えている人の後押しになれればと考えています。
▼その他にもご意見・ご要望がある方はこちらからお声がけをお願いいたします
![[政策方針] 皆様の困りごとに応えるため](image/policy_4.png)
この4年間も障がいある方やそのご家族、不登校や街の改善点など、様々なご相談を受けてまいりました。
私自身、仕事や人間関係で上手くいかず、挫折や苦悩も経験し、長女に生まれてすぐに障がいがわかり心が疲弊した時、家族や様々な関係機関、そして行政の皆さまに本当に救われました。
人によって様々な想いや悩みがありますが、その声・想いを理解できる人間でありたい。そして行政にその声・想いを届け、1人でも多くの方の困りごとに応えていきたいと考えています。
[やりたいこと/興味があること] ※ 各項目をクリックすると詳細をご覧になれます
「自分はどこに相談にいけばいいのだろうか?」「誰が聞いてくれるの?」ということを考えていては後手後手に回ってしまいます。「ここで」という相談から手助けまでをワンストップで行える窓口づくりから、縦割りをなくすような組織の改革、解決に至るまでの手助けとなる専門職である、ソーシャルワーカーの配置を進めていきたいと考えています。
「その気持ちわかる」「うちもおんなじ」ということは、似たような境遇や悩みを抱えている方でなければわかっていただけないこともあります。そして自分が思っている以上に、意外と身近にいらっしゃることもあります。
同じ障がいや疾病、依存症、子育ての悩み、ケアラーや介護、家族のことなどをお互いに「わかる」みんなで話をすることで、気持ちが軽くなることもあります。そんなお互いを支え合う「ピアサポート」を推進していきます。
視覚や聴覚に障がいのある方への情報発信はまだまだ十分とは言えませんが、手話通訳やAIによる同時通訳など、少しずつ進んできております。ですが文字の認識が苦手なディスレクシアの方や、知的障がいのある方に対しても十分に情報が行き渡っているかは疑問ですので、今以上に情報発信のツールなど工夫をこらすことが必要だと考えます。
「誰にでもわかりやすい情報発信」は、結果的に市民の皆さまに対してもわかりやすい情報発信に繋がっていきます。
総社市は15年連続の転入超過が続き人口が増加傾向にあります。一方でで隣近所、地域の方とのコミュニケーションが希薄化は顕著に現れています。
地域の方々に見守られ子どもたちが育つように、独居、高齢な方、障害のある方、外国/県外出身者の方も、みんなでお互いに見守り支えあうことがこれからの市に必要なことだと考えています。
そのために地域コミュニティーを今一度見直し改善していくことで、お互い様の関係を築けるアイデアを考えていきます。
総社市の重点施策のひとつである「障がい者千五百人雇用」がありますが、その就労までの過程において、個々の個性をや特性を伸ばすための「療育、発達支援」が重要となります。その環境をより良くすることで、就労の質を上げていき就労支援だけでなく、自立ができるような創業のサポート、また利用者の皆様が長く働けるよう事業所に対してもサポートできる体制を確立していき、より多くの方が生きがいをもてるよう尽力してまいります。
▼その他にもご意見・ご要望がある方はこちらからお声がけをお願いいたします






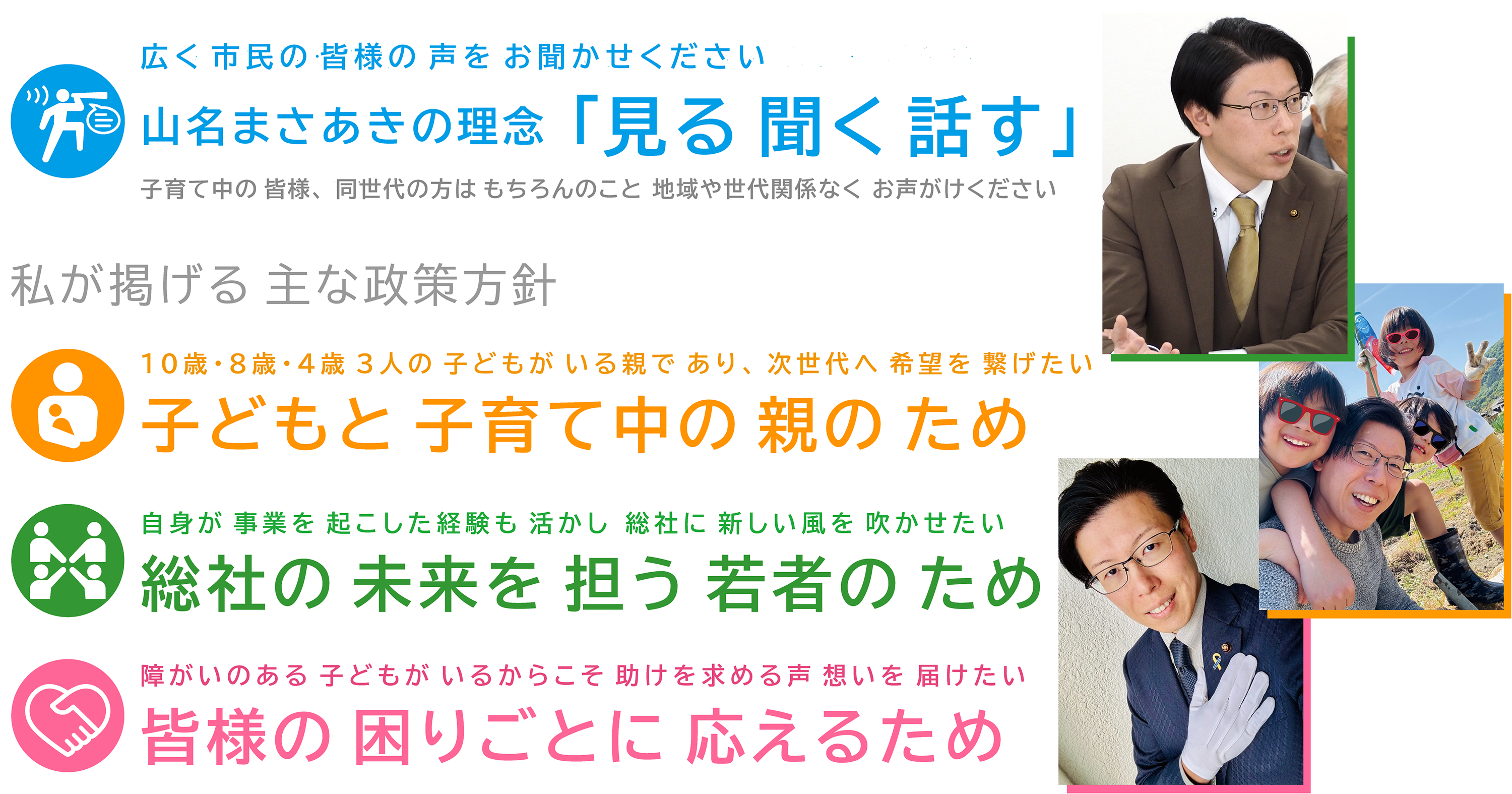
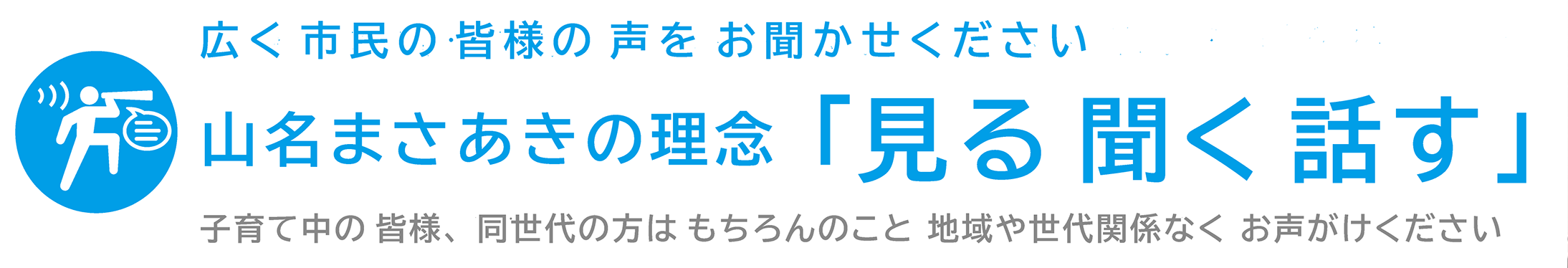






![[政策方針]子どもと子育て中の親のため](image/policy_2.png)
![[政策方針]総社の未来を担う若者のため](image/policy_3.png)
![[政策方針] 皆様の困りごとに応えるため](image/policy_4.png)